お金の“当たり前”は、時代ごとに変わる
こんにちは、ヤクスンです。
僕は清掃業を営んでいますが、この仕事を始めてから、
お金の見え方が大きく変わりました。
きっかけは「昔の常識は今の非常識になる」という実感です。
30年前の常識は今の非常識
昭和の終わりに生まれた僕が学生時代を過ごしたのは、ちょうど平成の中盤。
当時はまだ「会社に入って定年まで勤めれば一生安泰」という空気が色濃く残っていました。
景気はバブル崩壊後で多少の不景気感はあったものの、
ボーナスも年金も“あるのが当たり前”という感覚が社会に根付いていました。
しかし平成の終盤から令和と時代が移り変わるにつれ、状況は大きく変わります。
終身雇用は崩れ、ボーナスや退職金も企業によっては大幅縮小。
「会社や国が守ってくれる」という土台は、もはや幻想に近い存在になってしまいました。
僕が痛感した「守ってくれる人はいない」現実
独立してからは特に、
病気になっても有給はないし、退職金もゼロ。
自分の身は自分で守らなければならない現実に直面しました。
会社員時代は気にも留めなかった年金制度や税金の仕組み、
医療保険や労災のことも、全部“自分事”になりました。
学校では習わない「お金の筋トレ」
僕は正直、こういうことを学校で習った記憶がありません。
数学の公式は覚えても、
給料から引かれる税金や、保険の選び方は習ってこなかった。
だからこそ今は、お金の知識を筋トレのように鍛える必要があると感じています。
時代ごとにルールが変わるゲームで勝ち残るためには、
最新のルールを知り、自分なりの作戦を持つことが不可欠です。
これからのお金の付き合い方
これからの時代は、
- 収入源をひとつに絞らない
- 支出を数字で把握する
- お金の流れを“経営者の視点”で見る
この3つが鍵になると思っています。
特に3つ目は重要で、
「自分株式会社」としての貸借対照表(資産・負債)と損益計算書(収入・支出)を頭の中に持つこと。
これは事業者だけでなく、会社員や主婦でも有効です。
まとめ
お金の常識は、時代ごとにリセットされる。
昭和・平成・令和、それぞれの時代に合わせた戦い方が必要です。
次回は、「なぜ今は誰もが“経営者”にならざるを得ないのか」というテーマで、
さらに踏み込んでお話しします。

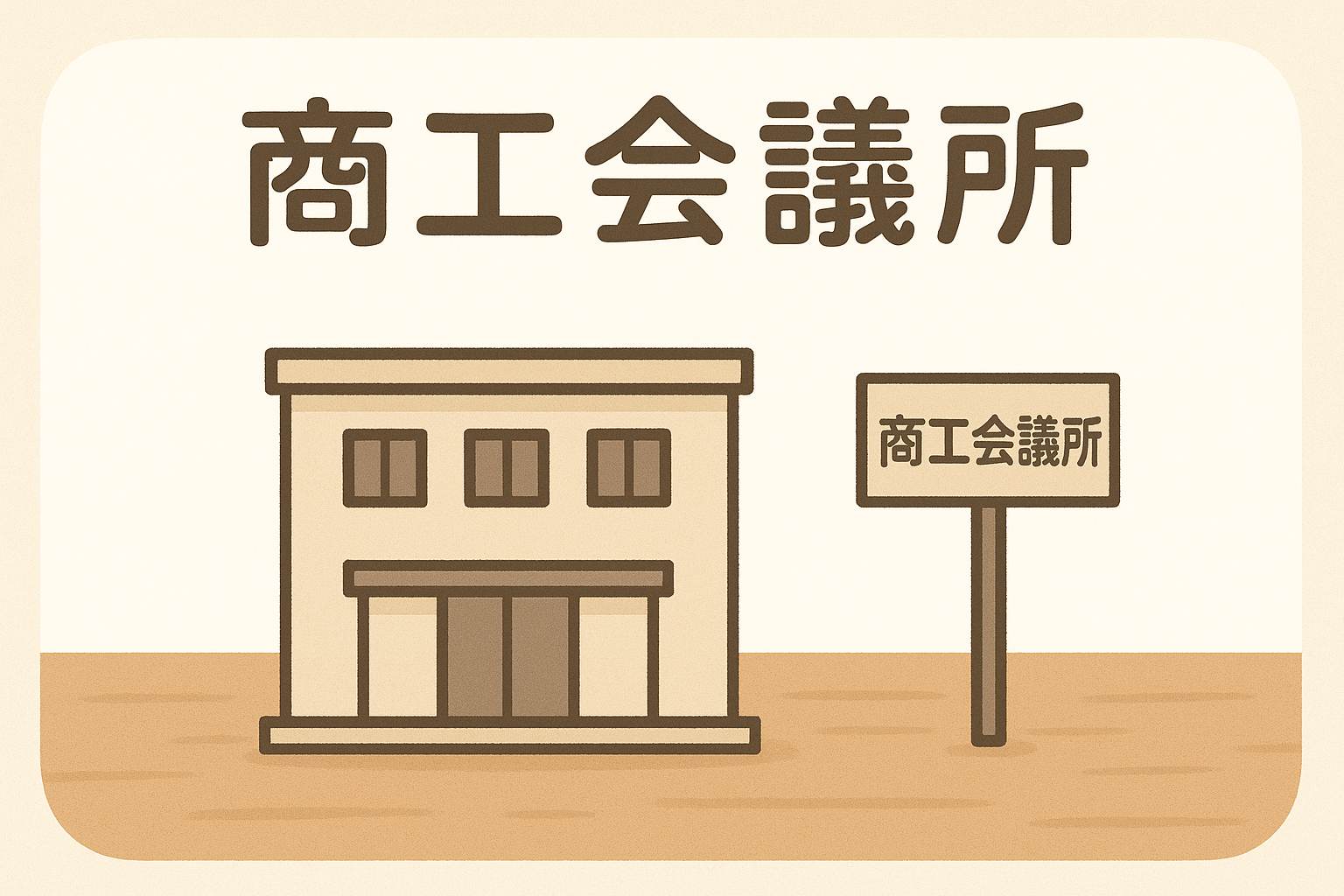

コメント